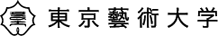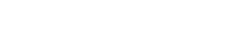① DOORを受講しようと思った理由
私がDOORを受講したのは、福祉の仕事をする中で、福祉だけでは解決できない社会問題の壁を感じたからです。
私は現在横浜市で生活保護ケースワーカーをしています。私が行政の福祉の仕事をしたいと考えたのは、東日本大震災がきっかけのひとつでした。震災の前まで、芸術や出版分野への就職を考えていましたが、震災をきっかけに漠然と「芸術は無力なのではないか」と思い、いま困っている人に直接支援を届ける仕事がしたいと思うようになりました。
実際に福祉の仕事をする中で、助けを求めづらい社会の仕組みや空気を感じ、社会がこのような空気である限り、個別の支援だけでは課題を解決できないと思いました。どんな方法で社会の空気を作ればよいのか、と考えた時、幼い頃に友人を作ることが苦手だった私が絵を描いていたら自然と友人ができていたという体験など、私自身がアートに救われてきたことを思い出し、アートには人と人との壁を超える力があるのではないかと思いました。
かつて私が“無力”と思っていた芸術が、実は問題をじっくり解決していく種になるのではないかと考え、DOORを受講しました。
② 印象に残っている講義や実習
選択授業「ケア実践場面分析演習」では、いくつかあるテーマのうち「貧困」を選んで、グループで企画制作を行いました。実際に上野周辺地域でフィールドワークを行い、メンバーがそれぞれの得意分野を活かして企画を形にしていく、という小さなアートプロジェクトを体験できました。グループで意見をすり合わせていくのは大変でもありましたが、今後の活動にも生かせる学びになりました。アートには、行き詰っていた福祉の課題と別の分野をかけあわせたり、言葉で伝えることが困難な価値や社会問題を表現し多くの人が関わるきっかけをつくる力があるのだと考えるようになりました。
また、特講「クロッキー」では、受講生同士で顔や身体を描き合う実習が印象に残っています。どの部分から描くかという話題になった際、「魅力的な部分から描く」と話していた受講生がいました。私も同じようにしてみたところ、それまでよりもバランスが取れるようになりました。これは絵を描くことに限らず、人を支援するときも、足りない部分ではなく豊かな部分を中心に見据えることでうまくいくこともあるのではないか、と思いました。
③ 仕事、生活、学業とDOORとの両立について
職場ではDOORを受講することを伝え、フレックスタイムを取ることで毎週の必修授業に出席することができました。忙しい時は、家事をしながら聞くだけの参加など、柔軟に参加しました。応援してくれた夫や職場の方々に感謝しています。
また、DOORで学んだことは仕事にも活かすことができると感じています。福祉の仕事をしていると、どうしても足りないものに注目しがちですが、アートの視点を持つと豊かさへのアンテナが高くなります。直接アートとは関係ない仕事をしていても、アートの視点を思い出すことで、偏見や閉鎖的な見方を揺さぶることになるのではないでしょうか。仕事以外にも、個人的に「ソーシャルワーカーの処方本」という活動をマイペースに続けているのですが、今後の方向性が定めることができました。
まず私にできることは、支援、コミュニケーションを、アートのように、楽しんで面白がってやってみることなのかもしれないと思っています。