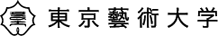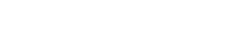1978年千葉県生まれ。
東京農業大学農学部卒業。日本社会事業学校研究科修了。千葉大学看護学部中途退学。
千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了。(学術修士)
2001年、社会福祉法人福祉楽団を設立し、特別養護老人ホームの生活相談員、施設長などを経て、現在、理事長。
2012年、株式会社恋する豚研究所を設立、現在、代表取締役。
現在、千葉大学非常勤講師、京都大学こころの未来研究センター連携研究員、ナイチンゲール看護研究所研究員。
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士。
- 必修科目
- ケア原論
2022
11/7
ケア原論11「赤ん坊の世話 / 越境する福祉ー社会過程への処方箋ー」
講師:
飯田大輔(社会福祉法人福祉楽団 理事長)

最終回のケア原論では、福祉楽団の飯田大輔さんにお話しいただきました。
前半では、子どもを対象にしたケアについて、ナイチンゲールの論から「生活を整える」ことをベースにお話しいただきました。
保育・看護・介護に置いて共通する目的は「生活を整える」ことです。人間は未熟な状態で生まれてくるため、社会や文化などの適切な刺激を受けながら育てられることが大切です。その基盤は言葉であり、赤ん坊には言葉をかけることが子どもの持てる力を刺激することになります。肌の触れ合いやおんぶや抱っこなどの皮膚を通した刺激を行うことで子どもにとって安心感のベースができ、愛着形成や人間の発達に繋がります。
講義の後半では、飯田さんが行う事業の一つである「恋する豚研究所」についてご紹介いただきました。
「恋する豚研究所」では豚の養育からハム製造、食の体験まで多岐にわたる展開をしており、「おいしいものをつくる」ことを大切にしています。また、障がいがある方の雇用も行い、月給10万円程度支払える仕事を作ることで「稼げる仕組みをつくって福祉を組み込む」ことに取り組んでいます。
また、少年院を出所して行き先がない方や、様々な複雑な問題を抱えた方に対する支援や雇用についてもお話しいただきました。問題を抱えた方に対しては包括的な相談支援を行い、当事者の立場に立って伴走することを大切にしています。こういったソーシャルワークを適切に行うためにも「生活を整える」視点が必要です。生活が整うことで心が整うことに繋がる、と飯田さんは言います。
近年、全国的に児童虐待の件数が増えている中で、子どもへの福祉は後回しにされがちな現状があるそうです。そういった中で、現在、飯田さんは虐待を受けた子どものための児童養護施設と一時保護所を設立しています。
「福祉はあくまでツールであり、その中心には人がある」と飯田さんは主張されます。誰もがその人らしく住み慣れた地域で生活できるように活動していくことに繋がってほしい、と講義を締め括られました。
前半では、子どもを対象にしたケアについて、ナイチンゲールの論から「生活を整える」ことをベースにお話しいただきました。
保育・看護・介護に置いて共通する目的は「生活を整える」ことです。人間は未熟な状態で生まれてくるため、社会や文化などの適切な刺激を受けながら育てられることが大切です。その基盤は言葉であり、赤ん坊には言葉をかけることが子どもの持てる力を刺激することになります。肌の触れ合いやおんぶや抱っこなどの皮膚を通した刺激を行うことで子どもにとって安心感のベースができ、愛着形成や人間の発達に繋がります。
講義の後半では、飯田さんが行う事業の一つである「恋する豚研究所」についてご紹介いただきました。
「恋する豚研究所」では豚の養育からハム製造、食の体験まで多岐にわたる展開をしており、「おいしいものをつくる」ことを大切にしています。また、障がいがある方の雇用も行い、月給10万円程度支払える仕事を作ることで「稼げる仕組みをつくって福祉を組み込む」ことに取り組んでいます。
また、少年院を出所して行き先がない方や、様々な複雑な問題を抱えた方に対する支援や雇用についてもお話しいただきました。問題を抱えた方に対しては包括的な相談支援を行い、当事者の立場に立って伴走することを大切にしています。こういったソーシャルワークを適切に行うためにも「生活を整える」視点が必要です。生活が整うことで心が整うことに繋がる、と飯田さんは言います。
近年、全国的に児童虐待の件数が増えている中で、子どもへの福祉は後回しにされがちな現状があるそうです。そういった中で、現在、飯田さんは虐待を受けた子どものための児童養護施設と一時保護所を設立しています。
「福祉はあくまでツールであり、その中心には人がある」と飯田さんは主張されます。誰もがその人らしく住み慣れた地域で生活できるように活動していくことに繋がってほしい、と講義を締め括られました。
講師プロフィール
社会福祉法人福祉楽団 理事長