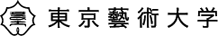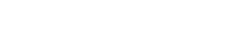- 必修科目
- ダイバーシティ実践論
ダイバーシティ実践論14「古代ギリシア彫刻に見る男性像・女性像・両性具有像・・・ヌードと着衣」

今年度の「ダイバーシティ実践論」の最終回では、東京藝術大学美術学部教授の布施英利先生をお招きしました。
東京藝術大学には、人体表現を学ぶための「美術解剖学」という授業があります。布施先生が担当されているこの授業では、筋肉や骨の構造を理解し、表現を行う上での基礎を身につけていきます。今回の講義では、解剖学の視点から古代ギリシャ彫刻の身体表現の多様性を通じて、美術や芸術の本質についてお話しいただきました。
古代ギリシャの女性彫刻像といえば、ヌード像であるミロのヴィーナスが広く知られています。しかし、アルカイク時代から厳格様式時代のギリシャ美術の中心的な時代ににおいては、女性のヌード像は存在せず、ミロのヴィーナスはヘレニズム時代末期に製作されてています。
布施先生によると、古代ギリシャでは人体をあるがままに造形することで、人体の中に神や宇宙の真理を見出すという考えがありました。また、男性・女性像だけでなく、両性具有像も彫刻として表現されていました。
古代ギリシャ彫刻は人体表現において高い技術を誇り、特に男性のヌード像には解剖学的な知識が反映されています。これは、古代ギリシャを起源とするオリンピック競技者が裸体で競技を行っていたことと関係があり、当時の彫刻家たちは鍛え上げられた競技者の身体の動きから人体を学んでいました。
講義の締めくくりにあたり、布施先生は「芸術の本質とは何か」という問いを受講生に投げかけ、「芸術の本質は『嘘』の力にある」と語られました。異質なものを組み合わせて新たな形態を創造することが芸術の力であり、それが感動を生む要因となるのです。ミロのヴィーナスやモナリザに見られるように、時代的・性別的な様式の交差が、時代を超えて多くの人の心を捉える力になっているのではないか、と布施先生は強調されました。
この講義を通じて、ケアの基礎である「観察する」ことの重要性を、美術を通じたダイバーシティの視点から学び、芸術が持つ意味や、人間の身体表現の歴史についての理解を深める貴重な時間となりました。布施先生の独特な語り口によって古代ギリシャにおける芸術の変遷も深掘りする、DOORの一年間を締めくくる大変意義のある講義となりました。