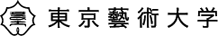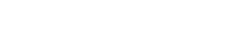1972年福島県福島市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。1996年より福島県立博物館に勤務。専門は美術工芸。2010〜2012年、会津の文化資源である「漆」をテーマとした『会津・漆の芸術祭』を企画・運営。東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故後は、『いいたてミュージアム(いいたてまでいの会)』『はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト(はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト実行委員会)』『福島藝術計画×Art Support Tohoku-Tokyo(東京都/福島県)』など、文化・芸術による福島の復興と再生を目的とするアートプロジェクトに携わった。近年は、福島県立博物館を事務局とした『ライフミュージアムネットワーク』『ポリフォニックミュージアム』に取り組み、2011年以降の学びをミュージアムを基盤として未来に活かす活動を続けている。
- 必修科目
- ダイバーシティ実践論
2023
1/16
ダイバーシティ実践論13「震災と博物館とアートプロジェクト」
講師:
小林めぐみ(福島県立博物館専門学芸員)

第13回目のダイバーシティ実践論は、福島県立博物館専門学芸員の小林めぐみさんにお越しいただきました。福島県立博物館では、ミュージアムとして震災に向き合う活動としてアートプロジェクトと震災遺産を収集する事業を行っており、今回はアートプロジェクトの取り組みについてお話しいただきました。
福島県立博物館は入館者の減少に対する対策として地域との連携を行い、博物館機能を活用して、会津の文化資源である漆をテーマとした「会津・漆芸術祭」を2010年からスタートさせました。
しかし、2011年の東日本大震災を受けて、博物館の活動方針は大きく方向転換することになりました。
震災直後、被災された方たちが一時避難所に避難している中で、福島県立博物館は「HEART MARK VIEWING」という取り組みに参加することとなりました。全国からの応援メッセージをタペストリーにしたものを避難所に飾るという取り組みです。
このような取り組みを行う中で、2011年の漆芸術祭は「東北へのエール」をテーマとし、全国からの東北への応援やメッセージの受け皿として芸術祭は継続されました。
小林さんは、震災後の世間からの福島に対するマイナスイメージが広がっていることを感じていたといいます。そのため、地域の文化や歴史・自然の美しさを背景にしたワークショップを意識的に行っていたそうです。
2012年からは、「はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト」を行う中で、小林さんは「いろんな方たちが集まる理由になる場」や「自分たちの故郷のことを共有する理由になるような場」をつくるためのワークショップを行ってきました。このプロジェクトでは、震災と原発事故のことをアーティストの表現で作品として残し、伝えていく活動も行っています。震災のことを作家の表現を介して伝えることで、観る人の中に能動的な動きがあったといいます。
福島県立博物館では、近年の取り組みとして「いのち」と「くらし」にミュージアムとして向き合うために、「ライフミュージアムネットワーク」を行い、福島の歴史を掘り下げるためのリサーチや、様々な人と福島のことを考える場所を作ることで、ミュージアムが地域の方達の活動の場として機能するために模索してきました。
小林さんは震災以降の活動を行う中で、文化的なものが後回しに考えられがちなものでもある、という場面に直面したこともあったそうです。「しかし、ミュージアムでの活動を通じて、文化というものの意義を改めて皆さんに伝えていきたい」とお話しされました。
小林さんは「調査」「収集」「展示」「教育普及」といったミュージアムの役割についてお話しされる中で、「場づくり」がミュージアムの新たな役割であることをお話しされました。震災以降、フラットな対話の場をつくることで、様々な方が自己の内面を掘り下げて考えを共有することの大切さを実感したと言います。
震災後の福島県立博物館の活動を通じて、ミュージアムの機能が地域の絆を深める役割を果たすとともに、文化活動の重要性についても再認識する時間となりました。
福島県立博物館は入館者の減少に対する対策として地域との連携を行い、博物館機能を活用して、会津の文化資源である漆をテーマとした「会津・漆芸術祭」を2010年からスタートさせました。
しかし、2011年の東日本大震災を受けて、博物館の活動方針は大きく方向転換することになりました。
震災直後、被災された方たちが一時避難所に避難している中で、福島県立博物館は「HEART MARK VIEWING」という取り組みに参加することとなりました。全国からの応援メッセージをタペストリーにしたものを避難所に飾るという取り組みです。
このような取り組みを行う中で、2011年の漆芸術祭は「東北へのエール」をテーマとし、全国からの東北への応援やメッセージの受け皿として芸術祭は継続されました。
小林さんは、震災後の世間からの福島に対するマイナスイメージが広がっていることを感じていたといいます。そのため、地域の文化や歴史・自然の美しさを背景にしたワークショップを意識的に行っていたそうです。
2012年からは、「はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト」を行う中で、小林さんは「いろんな方たちが集まる理由になる場」や「自分たちの故郷のことを共有する理由になるような場」をつくるためのワークショップを行ってきました。このプロジェクトでは、震災と原発事故のことをアーティストの表現で作品として残し、伝えていく活動も行っています。震災のことを作家の表現を介して伝えることで、観る人の中に能動的な動きがあったといいます。
福島県立博物館では、近年の取り組みとして「いのち」と「くらし」にミュージアムとして向き合うために、「ライフミュージアムネットワーク」を行い、福島の歴史を掘り下げるためのリサーチや、様々な人と福島のことを考える場所を作ることで、ミュージアムが地域の方達の活動の場として機能するために模索してきました。
小林さんは震災以降の活動を行う中で、文化的なものが後回しに考えられがちなものでもある、という場面に直面したこともあったそうです。「しかし、ミュージアムでの活動を通じて、文化というものの意義を改めて皆さんに伝えていきたい」とお話しされました。
小林さんは「調査」「収集」「展示」「教育普及」といったミュージアムの役割についてお話しされる中で、「場づくり」がミュージアムの新たな役割であることをお話しされました。震災以降、フラットな対話の場をつくることで、様々な方が自己の内面を掘り下げて考えを共有することの大切さを実感したと言います。
震災後の福島県立博物館の活動を通じて、ミュージアムの機能が地域の絆を深める役割を果たすとともに、文化活動の重要性についても再認識する時間となりました。
講師プロフィール

福島県立博物館専門学芸員