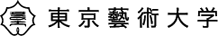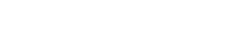ー受講のきっかけは何でしたか
平田:私は外国人向けの訪日ガイドをしているんですけれども、コロナでその仕事が全部なくなってしまって時間があったんです。個人的にアートに興味があり、時間もある中で勉強しようと思った時にふとDOORプロジェクトのホームページを募集の締め切りギリギリに見つけて滑り込みで書類を提出しました。
村田:私はもともと看護職なので医療で育ってきた人間なんですけれども、医療だけでは人を幸せにはできないなというのを常々感じていて。一度、現場を退いてもう少し知見を広げようと思っていたんです。職場の上司が美術展からDOORのチラシを持って帰ってきてくれて、それを見て面白そうだと思って応募しました。もともと私がいる医療の世界では「看護はアートである」という言葉があって。どういうことを言いたいのか、分かるようで分からないなという気持ちがずっとあったのですけど、芸術の世界の人たちと混じり合ったら、何か見つかるかなと思いました。
ー授業を受けてみて印象に残っていることはありますか?
平田:最初、「福祉×アート」って全然分からなかったんですが、次第にいろいろつながってきたように感じましたね。受講してみて、良い意味で予想外な授業でした。福祉といえば、どちらかと言えば教科書的な、理屈的な授業がメインかなと思っていたんですけれども、最初から当事者の方が登壇されたので驚きました。例えば認知症当事者の方が講師でいらしたりして。マイノリティーの方について、これまでは自分の中では分かっているつもりでいたけど全然分かっていなかったんです。木津英昭さんの講義のとき、「私は誰でしょう、全てです」と仰っていて衝撃的だったんです。あとはALS(筋萎縮性側索硬化症)当事者の真下貴久さんが登壇してくださったり。普通の授業だったらあり得ないじゃないですか。実際に医療の現場にいる村田さんはどうですか。
村田:人のことって座学でわかることは最低限で、その人の人となりなどを通してでしか分からない。さまざまな疾患や障害を抱えた方には仕事でお会いしたことはあるんですけれども、講義を受けてみて、私もたどり着いたのは平田さんが仰っていることと同じことでした。自分にも相手にも、分かったつもりで接したらだめだなと思いました。それが最終的には私のDOORでの一番の学びです。
ケア原論の近内悠太先生の講義がすごく分かりやすかったです。 「ケアというものはパンみたいに必須なものではなく、薔薇みたいに無駄なものです。でもケアをすることで人は人に戻る。」と仰っていたのが印象的でした。そうか、そういうものでいいんだよなと。医療も、なくてはならない人はいるんだけど、それだけだとただ生きるだけで。パンだけじゃ世の中の人はだめだ、薔薇はいるなと。私が目指しているケアはそれに近いものだなと。

村田加奈子さん
ーお二人は「ドキュメンタリー映像演習」を履修されていましたね
平田:ドキュメンタリー映像演習の授業は楽しかったですね。映像を撮るのって面白そうだと思って気軽に履修したんですが、授業を履修している人たちが個性的な人たちで、先生も面白かったです。前期の授業では毎週映画を見ようとか、映像の用語や技術的なことも学びました。その内容が、福祉やマイノリティの事を考えるという毎週月曜日の必修授業とすごく対照的で面白かったです。 カメラの使い方とか映像のアングルとか。今まで普通に見ていた映画やドラマが面白く見えるようになりましたね。
制作は、夏ごろからチームに分かれて始まりました。私が感覚過敏の擬似体験映像を制作するチームを選んだ理由は、ゲスト講師の橋口亜希子先生の感覚過敏についてのお話を伺って、実践ですぐ使ってもらえそうな社会に役立つようなものが作れそうだな、と思ったからですね。チームで音を録りに行ったり、Zoomで集まってミーティングをしたりしていましたね。当時の資料も保管してあるんですよ。

ー藝大生と一緒のチームでしたが、いかがでしたか?
村田:学生さんは皆可愛かったよね。良い人たちばかりでした。
平田:配役は村田さんが決めていたんだよね。学生さんは皆それぞれ自分の特技があったので、それぞれのメンバーの特性に合った役割を見つけていたのは村田さんだったかもしれないですね。
村田: 最初、演者は外の人たちから探してくるというイメージで、自分たちで役をやるということは考えてなかったんですよ。それが、なぜか自分たちで演じることになったんです。
平田:実は、ミーティングの回数自体はそんなに多くなかったんです。学生さんたちが課題で忙しくてなかなかタイミングが合わなくて、最初はちょっとドキドキしていました。でも、今となってはそのぐらいのペースで良かったかもしれないですね。全体としてはとにかく学生さんたちと一緒にできたのが楽しかったです。
村田:そうなんです。私は学生さんと関わりたくてDOORを受講したのもあったので。

平田麻利子さん
−お二人がメンバーと連絡を取り合ってスケジュール管理をされていましたね
平田:私たちは森内先生から勧められて、助監督として動いていました。学生さんたちは才能の塊で、クリエイティブなことを提案したり手を動かしたりというのがすごく得意なのだけれども、チームで作品を作るのは誰もが初めてだったんです。メンバー8人が全員かかわって、みんなで納得しながら完成できるように、コミュニケーションをとったりタイムマネジメントをしたりしていましたね。こういうことは社会人の方が得意ですもんね。
村田:私は、学生さんたちがのびのび表現できるようなサポートをできればと思いました。大まかなスケジュールは伝えるけど、学生さんが言ったことを聞いて、こういうことだよねと解釈したり反芻して、できるだけやりたいようにやってみる。それで一つのものができていったらいいなぁと思っていました。むしろ、学生さんたちが何を言い出すんだろうというのが面白かったなと。
平田:そうそう。村田さんのそのおおらかな姿勢が、学生さんたちの才能を最大限に引き出してくれていたように思いました。
村田:それぞれ皆、本当に持ち味がありましたよね。学生さんに話を振ったら必ず誰かから意見が出てきて、それぞれの面白い視点がありました。感覚過敏という、特別親近感がないであろう言葉をそれぞれによく咀嚼したと思っています。もしかしたら、なんとなくわからないでもない感覚だというところが皆にあったのかもしれない。感覚過敏について、皆、自分なりの表現をしてあのシナリオになったのかなと思います。
平田:私たち、皆真剣でしたね。衣装も、学生さんに衣装を探しておいてねと伝えたら探してきてくれて、小学校の時の制服を着てみましたと写真が送られてきたり。駅員さん役で着用した帽子も学生さんの手作りだったんです。映像内で流れている音楽も学生さんが作曲したものなんですよ。主役の子の演技も素晴らしかったです。全部が手作りでプロの仕事でした。
村田:主役の子が撮影の帰りがけ、ホームを歩いてる時に「駅構内にデコボコした道(点字ブロック)があるじゃないですか。自分が感覚過敏だったらここには立たないな(立つと気持ちが悪い)というのが分かる気がしました。」と言っていて。橋口先生もよく分かってきたね、と仰っていて。音が苦手、匂いが苦手、じゃなくて、そういうところですら色々感じるだろうからと。みんな本当に良い経験をさせてもらいました。
完成した作品「ハルの世界 〜感覚過敏のぼくが電車に乗るまで〜」
−受講してみてご自身の心境の変化はありましたか?
平田:制作に取り組んでいる内に、皆がそれぞれの立場で感覚過敏のことを考えていたように思います。
村田:これまで、感覚過敏のことは言葉としては知っていたし、なんとなく生きづらさというのも想像はしていたんです。実は私、この映像制作が終わった後に赤ちゃんを授かったのですが、最近までつわりがきつくて、匂いにすごく敏感になってしまったんですよ。出勤で電車に乗った時にいろんな匂いがきつくて生活するのにしんどくて、これも感覚過敏かなと思ったり。いろんな人がいろんなところで生きづらさをきっと感じているんだろうなと思いました。自分の経験と、感覚過敏の映像を作るということがすごくリンクした気がしています。制作した映像では、音や光が苦手だという人に焦点を当てていたけど、私みたいに匂いが苦手だったり、こういうことが苦手な人がいるんだろうなと思いながら街中を歩くようになりました。感覚って本人にしか分からないですもんね。
平田:感覚は、目には見えないものですよね。今は、ちょっとした匂いに過敏な方がいたりしても、私たちの感覚の10倍、20倍に感じるんだろうなと思うようになりました。橋口先生が、「感覚過敏の方は、一つの音が10倍に聞こえたりするんです」と仰っていて、そうか、それは辛いなと思いました。私は、恥ずかしながらこれまでヘルプマークの表示にあまり気づけていなくて。今はヘルプマークを身につけている人にすごく気づくようになって、そういう人を気にかけるようになりました。これはDOORプロジェクトを受講してなかったらあまり気づかなかったことかもしれないです。今は、前と違う感覚でいる気がします。

2022年11月
聞き手・撮影:北沢美樹(DOORプロジェクト)