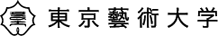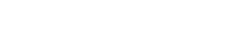― 集合住宅という場
「パフォーマーが、ナマの時間、ナマの表現をすること」
柳さんが「時間軸のある作品」と表現するパフォーミングアーツは、劇場ではないところで展開されるのだという。
「例えば車の中とかです。僕が運転して、観客は後ろの席。途中で役者が助手席に乗って来るというシチュエーションの演劇で、日常をリアルに再演するんです」
ありふれた日常のなかで、演劇的に仕組まれた何かが起こる。それが生まれる瞬間は「エッジが効いていてアート性が高い」と柳さんは言う。
ファミリーレストランでそこに居ない誰かの悪口を言っている女子高生のグループ。学童保育に来ている子どもたちから垣間見えるそれぞれの暮らし。大型マンションを見上げるとたくさんの窓があって、その一つ一つの中で何かが起きている……。
「それぞれの物語が、街の中に無数にちりばめられている。いろいろな場所で、それが起こっているんです。物語がうごめいている。めまいがしそうです」
うごめく物語は、演劇的に仕組まれた「何か」によって、さらに観客という他者が介在することによって、劇場で演じられる演劇のような「強度」を持つ、と柳さんは言う。
そんぽの家s王子神谷はサービス付き高齢者向け住宅。高齢者のための集合住宅だ。介助や介護を必要とする人が多い。入居者は、それぞれそこに住む理由や人生の物語を背負っている。その「劇場(ハコ)」の中で何が起こっているのか、ハコは外部とどのようにつながるのか。そこに自分が入ることによって何かが起こるというのが、「アーティスト・イン・そんぽの家」応募の動機だった。
「全く白紙。やってみないとわからない、と思っていました」
201号室にひとりの「俳優」が住み始めたことによって、そんぼの家s王子神谷劇場の幕が上がった。
― berまぼろす
前年度に活動していたアーティストは食堂を使ってコミュニティカフェを開催していたので、新しく入った柳さんもそれをやってくれるものだと、入居者は期待していたようだった。
お茶を飲みながら交流をはじめた。「ニコニコして何でも聞いてくれる若いお兄ちゃん」の柳さんに、住民はいろんな話をしてくれた。ここでの暮らし、抱えている葛藤、家族から見放されたという痛み。お悩み相談会のようになることもあった。
それに耳を傾けながら、柳さんは悩む。ここで何ができるんだろう。このまま身の上話を聞いているだけでいいのか。しばらくして、「こちらから自分がこういう人間だということを示そう」と動きだすことにした。
そんぽの家sの中では、飲酒が禁じられているわけではない。しかし住民には、決まった時間にご飯を食べ、その後は部屋に戻るというルーティンのようなものがある。その流れを変えてみたいと思った柳さんは、バーを企画した。
名前は「berまぼろす」。「幻」の偏の横に平仮名の「す」を合体させて「まぼろす」と読ませた。場所はいつもの食堂だが、照明を工夫し、凝った飾りつけをしてガラッと雰囲気を変えた。
月1回開催。毎回、ディスコ、怪談ばなし、クリスマス、節分などテーマを変える。キャンプナイトの回はテントを持ち込んで、マシュマロ焼きも出した。「こんなものはじめて食べるわ」と恐る恐る手を出したお年寄りが「おいしい」と笑顔になった。
7月27日の「まぼろす」では、盆踊りをした。翌日に地域の盆おどりがあると聞いて、「練習しませんか」と参加をよびかけた。15人ほどが参加、そのうちふたりが、翌日の盆踊り会場に行くと言った。そんぽの家sのスタッフが同行するわけではないのでちょっと緊張したが、「ふたりだから、何かあっても自分でなんとかできるだろう」と腹をくくった。
車椅子に座ってニコニコしている100歳の峰岸さん。「かき氷、なつかしいわ」と声をあげる長谷川さん。自分たちの日常からエスケープして、「町内の日常」に参加するという非日常体験に、ふたりは高揚感を味わっているようだった。
―峰岸さん、渡井さん、梅村さんのスイッチ
峰岸さんは、編み物も得意だった。それを教えてくれたのは女性ヘルパーの日高さんだ。日高さんは休憩時間にも食堂にいて、住民とおしゃべりをしている情報通。「barで使う野菜はここで買うといいわよ」など、柳さんの活動にも協力的だった。
「峰岸さん、昔は、編み物の先生をしていたそうよ。すすめてみたら?」と言われ、声をかけてみると、峰岸さんは進んで編み針を手に取った。
地域の住区センターが主催する「住区まつり」から、そんぽの家sにも参加しませんかと声がかかった。そこで日々の暮らしを再現する展示をすることになり、峰岸さんは自ら「展示物」として座って編み物をした。編んだお守りは販売して、その売り上げは、「峰岸さんのおごり」のお茶会で、ありがたくみんなでごちそうになった。
マッサージ師だった渡井さんとは、「マッサージ屋さん」をオープンすることにした。普段は部屋で寝てばかりの渡井さんは、施設内のモデルルームに設営したマッサージの場に立つと背筋がぴんと伸びた。もちろん本当に営業するわけではないので、渡井さんの体調を見ながら10分くらいで、と決めてスタートしたのに、当の渡井さんが施術の手を止めない。「10分じゃダメ。このマッサージはこのようにやらないと」と理論的に主張する渡井さんは、表情も口調も、現役のマッサージ師のようだった。
「渡井さんのスイッチが入る瞬間を目撃したんです。かっこよかった」
マッサージ屋さんは、その後も毎週木曜日に開店した。
高校の英語教員だった梅村さんは、柳さんが活動をはじめてからほどなくして入居してきた。文学や美術に詳しく、話しているうちに仲良くなった。
ある日柳さんがアルバイトから帰ってくると、梅村さんがエレベーターの前に立ち尽くしている。両手には、いつも食事の時に自室から持参する醤油とウスターソース。壁に向かって独り言を言っていた。
どこか具合でも悪いのかと話しかけた柳さんに、梅村さんは「これがカタカナのトとンに見えるんだ」と、館内の案内図を示した。そんぽの家s王子神谷は、2棟が連結されて途中で折れ曲がったような形をしている。平面図が6階分並んでいて、それが「トントントン」と見えたようだった。
梅村さんは、それから1ヶ月ほどたったある日、緊急搬送されてそのままそんぽの家sを退去した。
柳さんは、「トントントン」を何人かに読みあげてもらい、その音源を梅村さんが立っていた場所で、人通りが多くなる食事時を狙って5日間にわたって流した。「何これ」「ゾクッとするね」などと、通りすがりの人が感想を述べ、キャプションを読んで、そこにいた梅村さんのことをひととき思い出す。音の上演が終わったあとも、キャプションは、梅村さんが暮らしていた記憶ととともに、まだそこにある。
― 垣根を飛び越える子どもたち
様々なイベントを仕掛けた柳さんは、イベントそのものよりも、その準備や片付けをしている時間に「日常のコミュニケーションを分かち合えている」と実感していた。
それを分かち合った相手は、入居者だけではなかった。「barまぼろす」の強力なスタッフは、地域の子どもたちだった。前年度のアーティストが活動終了間際に開催したスタンプラリーをきっかけに遊びに来るようになっていた子どもたちは、バーの設営や買い出しなどに大活躍した。出し物のときには出演者にもなった。そのうち毎週水曜日が「子どもカフェ」の日となり、そんぽの家sから提供を受けた緑色のエプロンをして店員をつとめるようにもなった。
常連の子どもは4人。それぞれが友達を連れてくることもある。高齢者ばかりの施設の中で、子ども達の存在はそれだけで異質だ。歓迎する人がいる一方で「うるさい」というクレームもある。そこで、段ボールの「パスポート」をつくった。名前と保護者の電話番号を記入し、そんぽの家s内での行動ルールを示した。パスポートを持たない子が来たら即日発行。発行は、柳さんかもうひとりのアーティスト楼さんがいるときだけに限った。
ちょうど『パプリカ』が爆発的にはやっていた。子どもたちは歌が好きで、身体を動かすことも得意。柳さんたちはオリジナルのテーマソング『ハロー』をつくって、みんなで歌って踊った。「スローモーション ローハイテンション」と、そんぽの家s内での行動の約束事も盛り込んだ。振付をしたのは子どもたちだ。
ぼうけんしよう
けいけんしよう
ふしぎなことおこりそうだね
― できなかったこと、そしてこれから
「子どもは風穴をあける。垣根を飛び越える生き物なんだとつくづく思いました」
1年間の活動の仕上げに入ろうとしていた2020年の2月、新型コロナ肺炎が広がり、子どもたちは出入りできなくなった。子どもたちがいることが当たり前になっていた住民からも「カフェないの?」「子どもたちは来ないの?」と訊かれる。
建物内に立ち入れないので、ガレージバンドをやることにした。学校が一斉休校になり行き場を失った子どもたちは、毎朝駐車場に来て練習をする。新曲にも取り組みはじめた。
「自分がそんぽの家を『卒業』するまでに、この曲は完成するだろうか?」
一抹の寂しさを感じながら、残りの日々を惜しむように、柳さんはギターを抱えて子どもたちのピアニカと一緒に歌った。
コロナ禍で実施できなくなったことはほかにもあった。住人の物語から演劇をつくるという企画で、「部屋演劇」をやる予定だった。若い頃劇団の研究生だったという男性ヘルパーの大塚さんや、子どもたちも手伝ってくれることになっていた。当初の上演予定日は3月19日、その頃には日本中が新型コロナで大騒ぎだった。結局、いくつかの活動をやり残したまま月末になってしまった。
柳さんがそんぽの家sを去る期日ギリギリの3月31日、ガレージバンド「ハルマチ」は、待望のデビューライブを実施。演奏を終えると、柳さんは楽器や荷物を車に積み込んで、住み慣れた王子神谷を後にした。子どもたちは、車が見えなくなるまで走って追いかけてくれた。1年間の「そんぽの家s王子神谷劇場」は、誰も想像しなかった劇的なフィナーレを迎えることになったのだった。
「そんぽの家sと地域とのこれからの関係性にとっては、僕よりも子どもたちのほうが責任重大ですよね。僕がここにいるのは1年だけど、地域の子どもたちはこの先もずっと付き合う可能性がある。大きくなったらここで働くと言っている子もいます。10年後、『私たち、なんか毎週ホームに行ってたよね?』と、子どもたちが思い出してくれたらいいな」
コミュニティのこれからを思い描く柳さん。丸い太縁眼鏡の奥の目が笑っている。
「このアーティスト・イン・そんぽの家sがずっと続いて、カフェをやっていた子のうち誰かが『第12代のアーティスト』になってくれたら面白いんだけどなぁ」