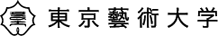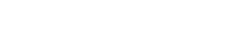― 社会の中のアート
上海の大学で環境デザインを学んだ楼婕琳さんは、卒業後の2015年に来日。日本語を勉強しながら美大進学の準備を進め、2017年に東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻に入学。いくつか訪問した中から、「直感で」日比野研究室を選んだ。
「先生と1時間も喋りました。そこで、作品そのものをつくるよりも、プロジェクト系のアートの方が新鮮だな、と思ったんです」
入学と同時にその年度からスタートしたDOORの1期生となり、社会人や学部生など多様な人々と一緒に学んだ。ここで、社会の中でのアートの役割について考えた。
2019年に大学院を修了してすぐ、そんぽの家s王子神谷に住み込んで制作活動をはじめた。
「アーティスト・イン・そんぽの家。高齢者の施設に若い人が住み込むこと自体がアートだなと。魅力的な試みだと思いました。」
2回見学し、前年度に活動していたアーティストにも会って話を聞いた。やっていけそうだと思って、活動計画をプランシートにして提出した。
― 壁絵日記
2017年4月早々に入居した。部屋は3階の301号室。ちょうど角の部分にあたり、バルコニーがやたらに長くて広かった。毎日1階の食堂におりていって食事をした。
楼さんはあまり社交的なほうではない。「どっちかといえば、ひきこもり」と言う。朝起きてすぐに、頭を日本語モードに切り替えるのも大変だった。そんな中で、高齢者ばかりの空間のなかに入った「異物」である自分に、何ができるのかと考えた。
具体的な目標はすぐには定まらなかったが、「とりあえず体を動かして何かしよう」と考えて、新しい暮らしに慣れたところで「絵日記」をはじめた。
廊下の壁にロール紙をはり、クレヨンなどの画材を持って行ってその場で描いていく。内容は自己紹介からはじまり、その日に出会った人、考えたこと、そんぽの家sのなかで起きたエピソード、イベントの様子など。もちろん絵も描いた。制作中に通りかかって、足を止めて眺めたり、声をかけてくる入居者もいる。時には「塗り絵しましょう」と、通りかかった入居者にクレヨンを渡すときもあった。
「1分くらいで、疲れちゃった、って言って止めてしまう方もいらっしゃるんですが」
1階の廊下からスタート、毎日描き続けてスペースがなくなったら次は2階。その後、3階、4階、5階と上がっていった。文字を読むのがおっくうな高齢者もいるので、文字を大きくしたり、カラフルにしたり、色々工夫をした。
「日記の内容そのものよりも、廊下で何かやっているというにぎわいのような雰囲気がよかったのかもしれません」
わざわざ感想を言いに来てくれる入居者もいた。まだ2階あたりで描いていたとき、5階の入居者から「いつ5階に来るの?」と訊かれたこともある。
毎日食堂で入居者と顔を合わせていたが、そこでできるコミュニケーションには限りがある。部屋食の人は食堂に来ないし、外食する人もいる。そういう人達とも、廊下ならば出会うことができた。
食事や就寝などの時間が決まっていて、自室と食堂の往復しかしない入居者が多い。生活リズムが決まっていることは、長生きの秘訣なのかもしれない。しかし、楼さんはそこに変化を作りたいと考えた。
「人は自分の存在があるところに足を運ぶんです」と楼さんは言う。
3階に住んでいるAさんのエピソードを、5階の絵日記に描く。誰かが「Aさんのことが5階に描いてあったよ」と教える。すると、Aさんは、普段は足を踏み入れない5階に行って自分の名前を探す。そうして新しい動線が作り出されるのだった。
― 月曜美術館
入居当初から何かに活用しようと考えていた自室の広くて長いバルコニーは、「月曜美術館」になった。楼さんの抽象画を展示して、毎週月曜日に公開した。自室の前に看板を出し、ドアを開けっぱなしにした。来館者は、楼さんが指しだすスケッチブックに名前を書いていく。バルコニーに出るには楼さんの部屋の中を通ることになるので、部屋でお茶を飲んでいく人もいた。
「みんな絵に対する興味が半分、私に対する興味が半分、くらいでしたね」
楼さんは、食堂でずっとおしゃべりをしているというのがちょっと苦手だった。キリがない。部屋にひきこもりたかった。そこで、逆に入居者を自分の部屋に迎え入れることを考えたのだ。
「みなさん、他人の部屋なので、遠慮があるんですよね。居座る人はいませんでした。差し入れのお菓子を持って来てくれたり、2回目からはバルコニーに出るためのスリッパを持参してくれる人もいました」
入居者たちのそういう気遣いや高い社会性は予期していなかったことで、楼さんを驚かせた。
月曜美術館の来館者は、入居者だけではなかった。職員やヘルパーさん、掃除のスタッフなどが覗きに来る。入居者は、普段は自分以外の人のヘルパーさんと交流することはないし、ホームの中では仕事の役割分担があるから、業務以外の人とのかかわりは発生しない。
「いろんな人がここに一緒にいるんだけど、同じことをする機会はなかったんです。そういう人たちが、何かを共有できる時間になった」
月曜美術館を企画した楼さん自身は、そこまでは考えてなかった。
5月から8月まで実施。途中で3回くらい展示替えもした。展示替えのたびに足を運ぶ人も、同じ作品を何度も見に来る人もいた。
7月の暑い最中に、「エレベーターガール」と題したパフォーマンスを2回実施した。エレベーターにずっと乗っていて、その中で絵を描く。もちろんいろんな人が乗って来るので、その人が着ている服の色をキャンバスに加えていった。
エレベーターは1階から6階まで乗っても30秒くらいだ。会話の時間をどこまで短くできるかという実験でもあった。
― 神さんとの「朝ドロ」
入居者の中に神さんという女性がいた。感情の起伏が激しく、しばしば言動が挑戦的になる。何でも集めて取っておく癖があって、自室はモノにあふれていた。
彼女はアートに強い興味関心を持っていて、自分でも10年くらいずっと絵を描き続けてきた。その神さんと、楼さんは毎朝食堂で一緒に絵を描いた。朝ドローイング、略して「朝ドロ」。
「神さんの作品は、生活の中の要素がモチーフになるんです。テレビに映った女優さんのアクセサリーを見て、そのデザインをどんどん描いている絵に取り入れていく。自分が集めたものや、枯れた花、お菓子の包み紙や広告など、身の回りにあるものを使って、コラージュ的な作品を作っていくんです。絵もすごい。私よりすごい。神さん、どうしてこういう絵が描けるのかと思いました」
神さんの作品を展示する「3階美術館」も開いた。3階の廊下に神さんの絵を展示して、エレベーター横に看板を出し、机を置いて存在をアピールした。最初は絵のタイトルを決めてもらうという企画を考えていたが、抽象画を「さっぱりわからん」と言う人がいたり、神さんへの遠慮があったりでうまくいかなかった。そこで、気に入った絵にシールを貼ってもらう方法に変えた。
ある認知症の入居者は、まるで自分の作品をつくるように1枚の絵にたくさんのシールを貼り続けた。パーキンソン病の入居者のところに往診した医師が、患者と一緒にシールを貼りに来てくれたこともあった。パーキンソン病の人にとっては、小さなシールを台紙からはがし、指先で狙ったところに貼り付けるというのは大変な作業だ。車椅子から懸命に体を伸ばしてシールを貼ろうとする姿に、楼さんは感動を覚えていた。
神さんとは、TURNフェス5(→リンク)に出展した。「神様の庭」と題し、楼さんがキュレーターとなって会場をデザインした。神さんの作品に詩をつけて展示、雲をあしらった空間のなかに神さんを迎えて、来場者と一緒に絵を描いた。楼さんにとっては、1年の活動のクライマックスとなる大きなイベントだった。
会場での神さんの様子には驚いた。
「しっかりしていて、社交性もばっちり。会話もちゃんとしている。施設にいるときより、外にいたほうが『普通』でした。私の方が逆に支えられたくらい」
TURNフェスでは、当事者よりもアーティストの作品のほうが目立っていることに、楼さんは疑問を持っていた。その中で、当事者でありアーティストである神さんと一緒に出展できたことは、とても意味があったと思っている。
楼さんは、いま、神さんの作品を商品化したいと考えている。商品のパッケージデザインを手掛ける会社に紹介した。社内で検討中だそうで、間もなく結果が出るはずだ。
― もっと自分を出して
12月になって終わりが見えてきた頃、楼さんは、施設の外から見えるところに展示をはじめた。建物の1階部分の太い柱の一つを白く塗った「はしら美術館」だ。
住んでいるうちに、入居者の動線がわかってきた。もっとたくさんの人の目に触れるように、多くの人がゴミ捨てに行くルート上で何かをしようと思いついた。最初は、ゴミを使った楼さん自作のドローイングを飾った。次に、入居者と一緒にローラーに墨をつけて紙の上をゴロゴロ転がして、書のアートのような作品をつくった。
2020年2月頃から、新型コロナウィルス感染予防のために思うように活動できなくなった。活動の集大成の時期だったから、心残りもあった。しかし楼さんは今、「アートは嬉しい時だけにやるものではない。悩んだり、何かがわからない時に表現するもの」だと言う。
そんぽの家sに飛び込んだ楼さんにとっては、施設内の人間関係の濃さは異文化でもある。そのなかで、他人との距離をどう保つのか、いかに個の時間を持てるのか。こうした楼さんの個人的悩みから着想して、作品が生まれてきた。、「月曜美術館」でも「エレベーターガール」でも、意外な効果が表れた。そういうことの繰り返しの1年だった。手ごたえはある。しかし同時に、ジレンマのようなものも感じているようだ。
「ここでの活動はもちろん私が希望したことですが、結局自分は、『アーティスト・イン・そんぽの家』という大きな作品の一部だったんです。私がどんな活動をしても、それは作品になる。だから、ここにいるのは自分じゃなくてもいいんじゃないかと。もっと『自分』を出したいという欲求が高まってきました」
4月からは、東北の現代美術館で学芸員としてインターンをすることが決まっている。
「自分がどんなアーティストになりたいかを確かめるため、今までとは違った立場に立ってみると、何かがわかるかもしれません」
近い目標としては、自分がキュレーションして神さんの展覧会を開催したいと、楼さんは思っている。