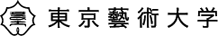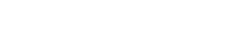ーDOORを受講したきっかけを教えてください
DOORを知ったのは、たまたま書店で見かけた書籍『ケアとアートの教室』を手に取ったのがきっかけでした。
現在はグルメサービスを運営する会社でプロダクト開発チームの企画職の仕事をしており、福祉やアートとはあまり直接的には関わらない領域です。そんな私がなぜこの本に興味を持ったかというと、きっかけは『聲の形』というアニメ映画でした。
この映画は、耳の聞こえない女の子とその子をいじめていた男の子が、高校生になって再会することをきっかけに、さまざまな人間模様を描いている作品です。
映画が公開されたのは2016年になるのですが、僕はこの作品を最近知って見るようになり、そこで大変な衝撃を受けたとともに、不思議と共感の気持ちになったことが印象に強く残っています。
特に、耳が聞こえない子といじめっ子との間に描かれていた、お互いの気持ちや意図の伝わらなさ・または違った形で伝わってしまうというようなコミュニケーションの問題は、普段の生活や仕事の中でもよくあることだなぁ…というのが共感した部分です。つまり根本的には「なぜ人と人の間にはこのようなコミュニケーションの問題が起こってしまうのだろうか」というテーマに興味を持つようになりました。
そこから「僕も実際に耳が聞こえない方ともコミュニケーションをとれるようになりたい」という気持ちで、手話検定を受けてみたり、CODA(Children of Deaf Adults:耳が聞こえないまたは聞こえにくい親のもとで育つ子どものこと)についての本を読んでみたりと、ちょっとずつ勉強をしてみました。
しかし実際の当事者の方と接する機会を作るなど、より一歩踏み込んでいくのにはハードルがあるなぁ…と感じていました。そんな時に、本屋でDOORについて紹介されている『ケアとアートの教室』を見つけ「実際の福祉現場に関われる機会があるなんて!これだ!」と直感的に思い、DOORの受講を志すようになりました。
ー実際にDOORを受講してみた感想を教えてください
ダイバーシティ実践論・ケア原論では、当事者の方や現場で実践されている方だからこそ語ることのできるリアルなお話を聞くことができて、普段の仕事や生活の中ではなかなか触れることのできない視点や価値観をインプットする機会になりました。この講義はオンラインで参加でき、平日の仕事終わりでも参加できる柔軟さがあったのもとても有難かったです。
座学以外にもDOORには実践的なワークが含まれた講座もあります。中にはデッサンの授業(DOOR特講:人体デッサン/2024年度まで開講)など本格的なアートの講義もあり、学生時代の美術の成績は大抵“3”と美的感性には疎い自分からすると、とても畏れ多い気持ちだったのですが…
せっかくの機会だからと!と、えいやで受講に踏み切ってみると実際はスキルがなくても問題はそこまでなく、どんなことを考えながら画材を手に取るのか?作っている瞬間の感覚はどんなものなのか?といったことを少しだけ体感できるような不思議な経験だったと振り返ります。
福祉とアートの共通点として、自分自身も含めた人の価値観を認めることや心の豊かさに向き合えることがあると私は思っています。
日常では得られない知識や実践だという新鮮さと一緒にそんな時間を過ごせるのが、私にとってのDOORの講座でした。
実際、講座の前後は不思議と、(仕事とか私生活とか…)もう少し頑張ってみよう…!とやる気の出る感覚があったのもよく覚えています。
ー印象に残っている授業や実習について教えてください
DOORを受講したモチベーションの1つが福祉現場での実践でした。そこで私は選択授業の1つである『ケア実践場面分析演習』(現在:ケア×フィールドワーク実践演習)を受講しました。そこでの経験がとても印象に残っています。
この演習は、上野周辺地域の福祉にまつわる課題を調査し、アートの力で解決を目指すというテーマをチームで取り組む実践的な授業になります。
私のチームは、上野地域の福祉施設『RESPEC(リスペク)』さんとの共同プロジェクトを行いました。リスペクさんは、日々の生活に難しさを感じている方や今後の社会生活(就労や復職など)を見据えた方が自立した生活を送ることを目指して、自立訓練・生活訓練のプログラムを提供している事業所です。
最初は“職業体験”と称して実際に開催されているプログラムに利用者さんに混じって参加してみたり、“藝大訪問企画”と題してリスペクのスタッフ・利用者さんと一緒に藝大の研究室/教室や作業室/美術館などを巡るツアーを開催しました。

藝大訪問企画にて正門で集合
さらにはDOORメンバー・リスペクさん・加えて上野地域に住む方々も巻き込んで、一緒に作品作りをするというコンセプトで行った『リスペク絵巻』の制作も思い出深いです。
雑誌やパンフレットといった身の回りの素材や、フロッタージュという技法を使って用意した素材を用いて、自由に絵巻を装飾していくという作品です。リスペクさんの事業所内に飾っていただき、利用者さんが好きな時に作品作りができるようにしたり、藝大散策企画などの機会を使ってDOORメンバーとも一緒に制作をしました。また時には、以前からリスペクさんと交流があった地域の銭湯にも展示させていただき、来店した方に自由に書き込みなどができるようにもしたことで、地域とも一緒にコラボした制作をした作品となりました。
真剣に作品づくりに取り組まれている様子や、和気藹々と作品を囲んで話している様子をみると、そこに立場の垣根などはなく一緒にものづくりができたと感じています。そんな経験ができたことがとても嬉しかったです。

フィールドワークでフロッタージュをしている様子
ー受講してみてご自身の心境の変化などがあれば教えてください
私は普段の仕事ではWebサービスやモバイルアプリの開発に携わっているのですが広義の意味ではものづくりをしています。そういった意味では先ほど紹介したリスペク絵巻の制作もものづくり、しかし環境や価値観は大きく異なります。
実際会社では、ユーザーに役立つものを作り喜んでもらうこと・それにより収益が上がり会社が成長すること・評価されスキル/給料が上がっていくこと…こういったことが仕事をする理由になるのですが、全てがうまくいくとは限らないし時には伸び悩む時もあると思います。私もDOORを受講したタイミングがまさにそんな悩みを抱えていた時期でもありました。
そんな折に、DOORの制作の過程で特に印象に残っている風景があります。
それは絵巻の制作をしている最中に周りを見渡した時に、リスペクのスタッフの方も利用者の方もDOORメンバーも、みんな自分の作った作品を見ながら、ちょっと照れ臭くも“誇らしそうな顔”をしている風景です。
その時皆さんがどんなことを考えて感じていたか全ては分かりませんが、そのちょっとした誇らしさはものづくりをする根源的な理由なのではないかと、腑に落ちたのです。作ったものを見て・作ったものが使われている姿を見て、自分で天才だな〜!と思う、そんな気持ちが原動力でも十分じゃないかと少し気が楽になった感覚でもあります。
そんな風にこのDOORの講義の時間やリスペクさんとの活動・制作の時間が、「ものづくりって良いな」と思える瞬間をたくさん蓄えることができたことが何よりの糧になり、なぜ自分はものづくりをするのだろう?という原点に立ち返ることができたことが自分にとって一番の大きな変化でした。

制作したリスペク絵巻 上野で開催されていた展覧会に出展しました
ー修了後の活動や展望があれば教えてください
受講を考えていた当時は、福祉の現場に関わる機会をDOORを通して作り、それが仕事なりプライベートなり何かしらの形で自分の生活にも繋がると良いなと考えていました。
ですが今は、すぐに福祉の現場に関わりたいという欲求よりは、むしろ今仕事にしているものづくりの現場で頑張ろう、という気持ちが強くなりました。
また『ケア実践場面分析演習』の最終講評の際に、とある講師の方からいただいたコメントで心に残っているものがあります。(※一言一句まで正確ではないですが…)
“あなたたちはいろんな活動をしてきたのだけど、これを違った観点で見ると『出会い方のデザイン』をしてきたんだと思う。幸せな出会い方をすれば関係は良好に築かれるし、不幸せな出会い方をすれば関係も保つことはできない。そんな風に、どうやって出会うかはその後の関係性を大きく左右する。リスペクとDOOR・リスペクと藝大・リスペクと地域施設。そうやって幸せな出会い方を作ったみなさんの活動は、意味のあるものだったと思います。”
ここで教えていただいた『出会い方のデザイン』という観点は、私の中でものづくりの1つの指針にもなりそうです。
私自身ものづくりに携わってはいるものの、特別優れたスキルや感性を持ち合わせているわけではなく、一人で何かを生み出せる人間ではないなと思っています。
ですがいろんな特性やスキル・役割を持った人が集まるものづくりの現場で、それぞれの関係性をつないで良い方向に流れるように働きかけることも、自分にできるものづくりだと考えるようになりました。
今の仕事にしても今後どんな活動をするにしても、DOORを通じて得られたものづくりと自分自身のあり方を大切にしていきたいと思います。

ケア実践場面分析演習のチームメンバーとの記念撮影