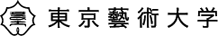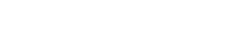ーDOORを受講したきっかけを教えてください
私は大学で電気工学を学び、半導体や太陽電池の生産技術開発に携わるエンジニアとしてキャリアをスタートしました。その後、転職先ではIoTを導入した生産ラインの開発を行う一方で、新規事業としてインテリア雑貨ブランド「stone+」を立ち上げ、アロマストーンの開発を行いました。銀座蔦屋でのPOP展示では、体験型プロダクトとして特別賞を頂きました。

新規事業stone+展示会@東京
ものづくりにおける「デザインの力」の大切さを実感し、京都芸術大学大学院でデザイン思考を学ぶ道に進みました。大学院での研究テーマは「ポゼッションリアリティによる共感形成のためのデザイン」で、(コロナ禍がきっかけで)オンライン環境でも共感を生み出せる仕組みを探求し、「オンラインZAKONE」という活動に結びつきました。その研究で、ケアに関わる仲間との出会いがあり、DOORの存在を知りました。未知の領域であった「アートとケア」の世界に飛び込むことは大きな挑戦でしたが、ワクワクとドキドキが入り混じる感情に背中を押され、直感的に受講を決意しました。
ー実際にDOORを受講してみた感想を教えてください
DOORでの学びは、毎回が新鮮な驚きと気づきの連続でした。当時の集中講義「人間形成学総論」「アートプロジェクト実践論」、特講の「ワークショップメイキング」、選択科目の「ケア×ソーシャリー・エンゲイジド・アート実践論」などを通じ、これまで触れてこなかった視点や方法論に出会い、とても刺激的でした。特にソーシャリー・エンゲイジド・アートは当初理解に苦しみましたが、先生方や仲間の実践から学ぶ中で、自分なりの解釈を得ることができたと思っています。
講義や演習を通じて、知識だけでなく「人との関わりの中で生まれる学び」の重要性を強く感じました。藝大という場には多彩なバックグラウンドを持つ人が集まり、互いの経験を交わし合うことで、単なる知識習得を超えた豊かな発見がありました。その過程で、自分自身の固定観念が揺さぶられ、思考の幅が広がっていく感覚がありました。
今振り返ると、DOORで過ごした時間は、知的好奇心と感性の両方を刺激し続けてくれる、とても貴重な体験だったと感じています。
*現在、「人間形成学総論」は選択科目として開講。「アートプロジェクト実践論」は2024年度までの開講。
ー印象に残っている授業や実習について教えてください
特に印象に残っているのは、奥山先生によるソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)の授業です。SEAの実践を通じて、アートが社会や人々の暮らしとどのように結びついていくのかを、具体的な事例や自分の実践を交えながら考える機会を得ました。
その中で出会ったアーティストとのつながりから、新規事業「stone+」とのコラボレーションとして、函館蔦屋で「香りとアートのワークショップ ~すりすり、ふわっと水彩であそぶ~」を実施することにつながりました。このワークショップは満席の好評を得て、アートとプロダクトが人々をつなぐ力を実感する出来事でした。
また、藝大の大石膏室での伊藤達矢先生の「DOOR特講:人体デッサン」(2024年度まで開講)も強く印象に残っています。私にとって、「観察し、手を動かし、身体を通して世界を捉える」という経験は新鮮であり、ものづくりの根源に立ち返る時間となりました。この経験は後にデッサンや油絵を描くことへのあこがれ、さらにはプロダクトデザインにおける触覚的な表現の探求にもつながっています。
DOORの授業は、単に知識を学ぶだけでなく、自分の活動を新しい方向に広げてくれる起点となりました。

香りと水彩画アートのワークショップ@函館蔦屋
−受講してみてご自身の心境の変化などがあれば教えてください
受講前は、エンジニアからデザインやアートへと関心を広げている最中で、どこか「異分野に挑むことへの不安」を抱いていました。しかしDOORを通じて、未知の領域に踏み込む行動が新しい可能性を切り拓く原動力になると実感しました。まさに考えてから行動するのではなく、まず行動することがやる気につながる。特に、アートを介してコミュニティや人々と関わる中で、「人との縁が次の縁を呼び、円となって広がっていく」という感覚を得られたのは大きな収穫です。
また、修了後も続く仲間とのネットワークは、自分の行動を後押しする支えとなっています。例えば、美術館勤務の同期とのつながりから糸紡ぎのコミュニティに参加したり、障害者支援施設の木工現場を訪問したりと、思いがけない出会いが行動のきっかけを与えてくれました。
DOORでの経験は、単なる学習にとどまらず、自分の心を動かし、行動するモチベーションを生み出してくれたと感じています。
不安よりも「変化を楽しもう」と思えるようになったことが、最大の心境の変化です。
ー修了後の活動や展望があれば教えてください
修了後は「アートとサイエンス、そしてケア」を行き来する挑戦を続けています。日常的に美術館を訪れ、身体で作品を感じる時間を大切にする一方で、東京大学松尾研究室のAI講義を受講し、人工知能の最先端を学んでいます。AIを活用して似顔絵を生成する試みなど、新しいテクノロジーと表現を掛け合わせる学びを行っています。
また、五感を通じた身体性の重要性を意識し、武蔵野美術大学油絵学科に通信入学してデッサンや油絵、フレスコ画を学び挑戦しています。伊藤先生のデッサンの授業がその大きなきっかけになりました。
さらに、趣味でサックスを習いながら音楽にも挑戦中です。
日比野学長が始められた「明後日朝顔プロジェクト」も残り種で、この夏も自宅で朝顔を育てています。自宅で咲いた朝顔の種を知人へ広げていければとも思っています。
これからも、アートを「こころの原動力」として信じ、人生100年時代・AI時代にふさわしい新しい表現やケアの形を模索していきたいと考えています。DOORで得た経験は、楽しく生きるための原動力であり、今なお挑戦し続ける勇気を与えてくれています。

2025年9月